
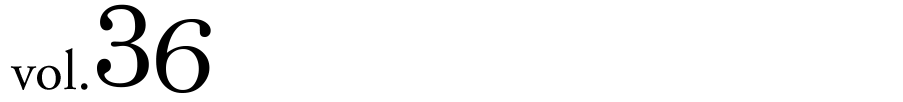
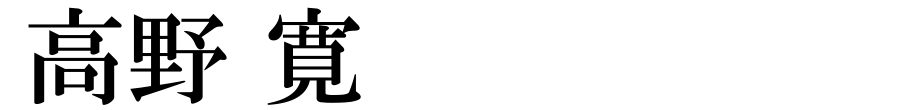
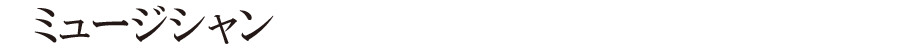

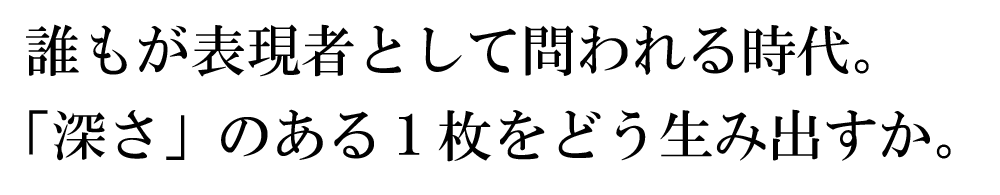
シンガー、ギタリスト、プロデューサーとして世代やジャンルを超え、多彩な音楽活動を行う高野寛さん。 メカ好きの父親の影響から写真を撮り始め、海外で撮り下ろした写真でフォトエッセイを刊行するなど、写真愛好家としての顔も持ちます。 誰もが手軽に写真や音楽を発信できるいま、どのような表現が必要だと感じているのでしょうか。
2021/10 取材・文:橋口弘(BAGN Inc.) 撮影:藤堂正寛
−音楽と写真の二つのジャンルを行き来する高野さんですが、最初に夢中になったのは写真だそうですね。
いまだに実家に防湿庫があるほどカメラ好きで、上等な一眼レフを持っていた父親の影響があります。 中学生だった頃、世間はスーパーカーブーム真っ只中。車のかっこいい姿を写真に収めたくて、貯金でカメラを手に入れました。 基本的な知識や技術は、当然父親から教わりましたね。次第に音楽へと興味が移ったので、写真からは一旦距離を置くことになるのですが。

−そこから、再び撮り始めるきっかけは何だったのでしょうか?
デビュー後の1989年、3枚目のアルバムのレコーディングをアメリカのウッドストックにある、トッド・ラングレン*のスタジオで行っていた時です。日本でいう軽井沢のような別荘地ですが、ただの田舎ではなく、ヒッピー時代よりもっと昔の開拓時代からアーティストコミューンがあったような場所です。10月頃にレコーディングしたのですが、紅葉がすごく綺麗で。40日間ほどの滞在中、秋の移り変わりを小さなカメラでずっと撮っていたんですね。それが思いのほか良かったので、CDのブックレットに数カット入れようということになり、そこから写真が面白くなっていきました。 海外に行って写真を撮る、ということがきっかけとしてとても大きかったと思います。翌冬には、カメラを新調して再訪。今と違って手軽にスマホで撮影して残せるものではなかったから、シャッターを押す瞬間もすごく考えましたね。いいなと思うものに出合い、シャッターを押すときのあの気持ちは、いま写真を撮るときの感覚とはまた違う気がします。旅から帰ってきて、どんなものが上がってくるかなとワクワクしながら待つ時間も楽しいし。思った通りだったり、予想外の仕上がりだったり、それも醍醐味でしたね。
トッド・ラングレン*
アメリカ人ミュージシャン。1970年代からヒット作をリリースするほか、プロデューサーとしても活躍。ロックの歴史に多大な影響を与え、2021年に「ロックの殿堂」入りした。

−旅先での写真が余計に愛おしくなりますね。写真を撮る時、ついつい惹かれてしまうモチーフはありますか?
空や動物など、自然のものをつい撮ってしまいますね。特に雲を眺めることが好きで、写真を撮らなくとも空を見上げている時間は長いと思います。
空を見ることは、東京にいながらも自然を感じることができる行為だからではないでしょうか。
僕の主観なので実際にはわからないのですが、この20年くらいで雲のコントラストがかなり変わった気がしていて。
沖縄などの亜熱帯地域でよく目にする虹が、東京でも頻繁に現れるようになったのは、ごく最近の傾向だと思います。
そして、光も強くなっている気がしています。こんなに眩しい光はあったかなと思うほど。
雲の陰影も昔と比べてとてもはっきりしていて、なんだかルネッサンスの絵画を見ているような印象さえあります。

−撮影時のマイルールはお持ちですか?
「撮っている」という自意識を消す、でしょうか。構えて撮らない方が面白い気がして、あくまでも通りすがりのなかでたまたま切り取ったものを残すという感覚ですね。
まるでハンティングのように、ある種偶然性も必要というか。
僕はフィルムとデジタル両方で撮るのですが、デジタルだとつい無尽蔵に撮りがちじゃないですか。
そのまま放ったらかして溜めっぱなし、見返しもしないことが一番もったいない。
撮る時も無駄にシャッターを切らないようにしています。プレビューで見返して、イマイチだなと思ったらすぐに消す。
それを持ち帰って、当日のうちに必ず現像する。そして、そこでもまた消していく。
デジタルは気をつけないとただのデータで終わってしまうから、そうならないように意識していますね。
大半は日常の記録に過ぎないけれど、その中からたまに作品が生まれるので、そのために続けています。


−写真も音楽も創作する高野さんにとって、二つの表現の関係性とは?
レコードで育ってきた身なので、特に高校や大学生の頃は、ジャケットのアートワークを眺めながら音を聴くことを習慣にしてきました。
MTVなどミュージックビデオが流行り始めてからも、いまと違ってたまにテレビで目にする程度。僕にとって音楽体験とは、アートワークを見ながら想像を膨らませるもの。
歌詞と音楽とアートワークとが、三位一体になっているというイメージなんです。
しかし、現在は動画がありふれています。ミュージックビデオを観て良い曲だなと思って、その後音だけ聞いても、意外に脳内再生されているのはビデオの追体験で、音のイメージではないことに気がつきました。
いわゆる視覚優位の時代で、音を中心に作っている身としてはなんだか少し歯痒いなと思うこともありますね。
−利便性とトレードオフなのでしょうね。
良い写真、良い音楽とは、なんだと思いますか?
個人によってまちまちだと思うんですが、やはり聞き流せないものとか、ハッと目に留まってまじまじと見つめてしまう写真など、自分が釘付けになる何かがそこにはあると思います。 違いがわかるには、ある程度のリファレンスとなる経験なり知識なりが必要ですよね。写真の良し悪しや深みが分かるようになったのは、音楽を始めて時間が経ち、表現というものに向き合い続けてきた結果でもありますし。 すべての領域でアートとしての深みのあるものを段々と見極められるようになってきたと思います。
−その「深さ」とは、どういう言葉に置き換えられますか?
時代を超えるもの、文化や人種などの背景を超えて響く何か。さまざまな基準はあるけれど、「普遍性」ということでしょうか。けれど、これがなかなか手強くて。
やはりいまのようにポリティカルコレクトネスという価値観が出てきて、それでもなお耐えうるかということもテーマになってきているし。
ネット上には作品づくりのマニュアルがたくさんアップされていて、誰でもアクセスできます。若い人が、いきなり完成度の高いものを初めから創れる良さもあります。
けれど、昔の人が試行錯誤の末、不器用に格闘し創り上げたものの凄みとは違う。良くも悪くも既視感があったり、リメイク的であったりしがちなので。
ものすごいものが出てきたな、という作品にはなかなか巡り合えなくなっている。みんなそこと戦っていると思うんですね、
新人もベテランも。一定のクオリティのものが溢れているという印象があります。そこから一線を越えることがとても難しくなっていて、プロの仕事の仕方もおそらく変わってきているのだと思います。
何が必要か、何ができるか、というのがみんな問われているのだと。


−なんだか、足音や湿度、その場の空気感が伝わってくるような写真ですね。
1994年、坂本龍一さんのワールドツアーにギタリストとして参加した、イタリア・フィレンツェ公演の合間での一枚です。 会場はフェリーニの映画に出てくるような移動式のサーカステントで、近くには河が流れていましたね。本番前の空き時間に、会場の近くを散歩していた老人を何気なく撮りました。 季節は、冬が始まりそうな秋の暮れ頃。東京とは全く異なる、フィレンツェの河のようにゆったり流れる時間が写し取られている気がします。27年前のモノクロ写真に焼き付けられた瞬間は、時が経つほど貴重なものに感じますね。 このプリントは100年くらい残るはずですが、それはやはりすごいことだと思います。

−モノとして時を刻む。それがプリントの持つ魅力でしょうか。
どんなにさり気ない瞬間でも、「もう戻らない時間」だということ。10年先にはどうなっているか分からないデジタルのデータとは違って、ずっと残り続けること。 プリントは、アナログとしての生命を持っている。 写真がきちんとオブジェクトになっているということですね。
−結局のところ、写真の面白さはなんだと考えますか?
奥は深いけれど、入口はごく身近なところにあるじゃないですか。スマホ以降の写真は特に。誰でも扱えるものなんだけれど、そこには際限ない深さがあり、誰でも喋れるような「言葉」と同じようなものじゃないかと思います。 ジャンクな言葉もあれば、一生の座右の銘となる言葉もある。エディットによっては、人を感動させることもできれば、人を傷つけてしまう可能性もありますよね。

−これからどんな写真を残していきたいですか?
撮ることで、現実を超えた瞬間すら残せるのが写真の一番の魅力だと最近は感じています。そのような、自分の意図を超えた写真が撮れたら嬉しいですね。
とはいえ、写真はあくまで趣味なので、ただ楽しくカメラと戯れていたい。
永遠のアマチュアカメラマンが目標です。時折、大物を釣り上げることがあるので、その大物の“魚拓”をたくさん残していきたいと考えています。
以前、ブラジルでレコーディング滞在中にリオ・デ・ジャネイロで撮った写真をまとめたフォトエッセイ集を出しました。
「#monochrome_tokio」*というハッシュタグをつけて、東京のさまざまな風景をモノクロにして撮るシリーズを撮りためているところなので、新しい写真集を作りたいですね。
「#monochrome_tokio」*
Instagramアカウント「takano_hiroshi」にて公開中。「#monochrome_tokio」でも検索できる。

高野寛
1964年生まれ。1988年ソロデビュー、これまでにベスト盤を含む22枚のソロアルバムをCDで発表。 ソロ作品のほか、世代やジャンルを超えたアーティストとのコラボレーションも多数制作。 ギタリストとしてもYMO、高橋幸宏、細野晴臣、TEI TOWA、星野源を初めとした数多くのアーティストのライブや録音に参加し、坂本龍一や宮沢和史のツアーメンバーとして延べ20カ国での演奏経験を持つ。 サウンドプロデューサーとしては小泉今日子、THE BOOM、森山直太朗、GRAPEVINE、のん などの作品を手がける。2018年4月より、京都精華大学ポピュラーカルチャー学部客員教授。
高野寛オフィシャルサイト
詳細:こちら